ミシガン大学家庭医学科日本家庭健康プログラム 研修報告
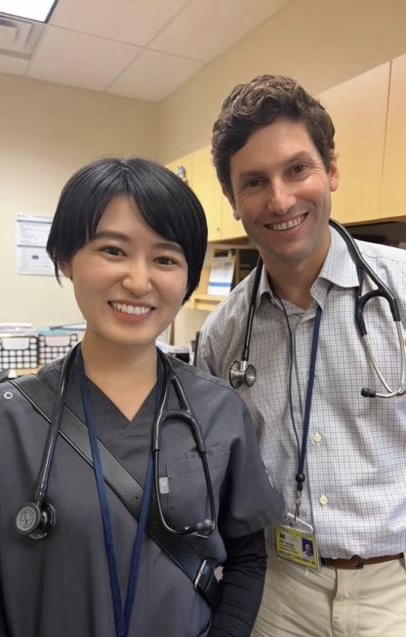
■【本研修の目標】
ミシガン大学家庭医学科の外来見学を通して、研修医はアメリカの家庭医の外来診察内容について学び、日本の家庭医との相違を理解する。又、アメリカでの家庭医療の仕組みを理解することで、現在の自身の属する環境を改善するための視点を獲得する。
■【研修内容のまとめと印象】
<Livonia Health Center>
・Little先生、清田先生、若井先生、Beduhn先生の診療を見学させていただきました。英語を話される地元の方で長い間通院されている患者さんもいらっしゃれば、ご家族で日本からお引っ越しされてきて間もない患者さんもいらっしゃったりと、背景が異なるさまざまな方々とお会いすることができました。日本のような学校での集団健診がないためか、日本人患者さんの診療ではお子さんの健康診断も多いなという印象でした。
・Annual Wellness Checkに来られていた80代の患者さんの診療では、最近の心配事は転倒することであるとお話されていたので、その方が通うことができそうなPT(Physical Therapist)さんのリハビリテーションを紹介されていました。私自身、日本で入院患者さんに急性期病院からリハビリテーションを専門的に行う病院への転院を勧めることはあっても、外来患者さんにリハビリテーションを行う施設を紹介する経験は今までなかったので印象的でした。
・Sports medicineでは、膝痛や股関節痛で悩んでいらっしゃる方々が関節内注射を行うことで痛みが和らぎ笑顔になって帰っていかれる姿を見ることができました。
・Procedure clinicでは、コルポスコピーや避妊インプラント、皮膚生検など、日本であれば産婦人科や皮膚科の先生に依頼するようなこともFamily medicineの領域で行われていることを学びました。
・診療されている先生方がAAFP(American Academy of Family Physicians)やUSPSTF(United States Preventive Services Task Force)などを活用されて患者さんに提供する情報を日々アップデートされていることも学びました。
・またスタッフシャドーイングとして看護師さん、Medical Assistantの方々、フロントの方々のお仕事を見学させていただきました。Michigan州では、日本の外来看護師さんと同様のお仕事を主にMedical Assistantの方々が行われていました。看護師さんのお仕事はお電話でのトリアージやポータルメッセージでの患者さんからの質問に答えたり、時には検査結果を伝えたり、処方箋を発行したりと日本の医師が行っている内容と重なる点もあり、日本の看護師さんとは患者さんに施行できる行為の幅が異なっていることに驚きました。
 Livonia Health Center外観 |
 Center内の様子 |
 診察室 |
<Domino’s Farms>
・Rew先生、Little先生、橋川先生、Shumer先生の診療を見学させていただきました。Livonia Health Centerよりは日本人の患者さんの受診は少ない印象でしたが、そのうちのお一人から、母国語である日本語で診療を受けられる素晴らしさを伺うことができました。自分自身の健康に関わる大事なことだからこそ、医師の発言を100%理解できる状況ではじめて安心できるのだと感じることができました。
・Integrative medicineはいままで学んだことのない分野であったため、患者さんに提案する処方についてもあまり聞き慣れないものが多く新鮮でした。
・印象的であった場面としては、同じ家族のお二方を健康診断で個別にひとりずつ診療した場面です。抑うつ傾向のある患者さんが、自身の気持ちをもう一方のご家族に伝える場を設けることをご希望されなかったので、ご家族の診療ではご家族の方ご自身の近況をお伺いする事のみにとどまりました。患者さん個人だけでなく家族も一緒にみることができる点がFamily medicineの良い点ではありますが、家族といえどもご本人の許可なしに診療内容を話すことはできず、家族間の問題解決の糸口となるものを何も提案することができない自分自身に歯痒さを感じました。
・余談にはなりますが、Domino’s Farmの“Domino”が日本でもよく見かけるDomino’s Pizzaの“Domino”であったことやスタッフ用のカフェテリアがあることは驚きでした。
 Domino’s Farms外観 |
 Family Medicine入口 |
 Cafeteria |
<Chelsea Retirement Community>
・ADL/IADLが自立しているエリア、IADLについては多少介助が必要なエリア、認知症の方々のエリア、看護や介護が必要なエリアと4つのエリアごとにご高齢の方々が一緒に住んでいらっしゃる一つの地域という感じでした。
・Nursing homeでは腰椎圧迫骨折でリハビリテーション目的に入院された患者さんにお会いしました。その方の基礎疾患である糖尿病のコントロールと疼痛コントロールのための病歴聴取を行う場面を見学させて頂きました。患者さんとは初対面でしたが、話している中で患者さんがかかりつけ医との関係性についてお気持ちを吐露する場面もあり、会話の中でそのお気持ちを引き出された清田先生の診療は凄いなと感じました。
・Chelsea Retirement Communityの施設内には、入居や入院されている方のためにお花を持って行けるよう様々な種類のお花を育てているお庭があり、素敵だなと思いました。ADLが自立した方々のエリアには、プールや体を動かせるジムのような場所も完備されていて驚きました。
 施設内のお庭 |
 お庭の様子 |
 施設内のジム |
■【このローテーションで最も学んだ・修得したこと】
・日常の外来診療で、患者さんが現時点で罹患している疾患に対して悪化しないようにサポートしていくことも大事なことですが、今後罹患しうる疾患について予防できるようサポートしていくことの大切さを学びました。
・がん予防のためのスクリーニング検査、感染予防のための予防接種、高齢者の転倒予防のためのリハビリテーションなどあらゆる予防の観点から患者さんに必要な情報を提供することを学びました。
・個人の身体的な面と精神的な面は繋がっていて、その個人を取り巻く社会的な面についても目を向ける必要があり、家庭医は患者さんの身体的な健康相談に乗るだけでなく、精神的な健康もサポートし、家庭内暴力やハラスメントなどの社会的な問題についてもカバーできる対応力が必要であることを学びました。
■【このローテーションで特に良かった点、自分が目指す家庭医になるためにプラスになった点】
・ローテーションで特に良かった点は2週間という短い期間で多くの先生方の診療を見学させていただくことができた点です。全く異なる背景を持った先生方が家庭医として働いていらっしゃるので、同じように診療をしていても先生方それぞれの雰囲気があって興味深かったです。
・私自身が目指しているのは、私が医師として向き合う方々から生きがいを引き出すお手伝いができる家庭医です。もちろん生死に関わるような疾患に罹患することで自身の生きがいについて考えるタイミングを持つこともあるかと思いますが、そのような状況に遭遇せずとも日常生活の中で自身の生きがいについて考えたり、自身が幸せであると感じる物事に気づくには、身体的にも精神的にも健康である状況が必要であると思います。
・健康な状態を維持し続けていくのに大切な予防という観点から予防接種やがんスクリーニング、リハビリテーションについて推奨していくことは日常診療にすぐに取り入れることができる部分であると感じました。
・日本では若年層は特に罹患している疾患がないとなかなか医療機関を受診する機会がないので、健康診断などで受診した際に、PHQ(Patient Health Questionnaire)-9などの質問票を用いて抑うつのスクリーニングを行った方が良いと思いました。
・私の身の回りの診療現場ではACP(Advance Care Planning)については、なかなか進んでいないと感じております。Annual wellness checkで用いられていた冊子を拝見して、1年に1回の健康診断での受診時や定期外来で時間がある時にご高齢の方々を対象に今後のことをどのように考えているのか、どのような最期を迎えたいと思っているのかをアンケート形式で尋ねてみることを始めてみたいと感じました。
■【このローテーション改善のために研修者ができること】
・今回の研修で学ばせていただいた貴重な経験を私自身が研修している病院の先生方向けに発信することだと考えています。
■【その他、印象に残ったこと、感じたこと】
・患者さんがポータルでカルテを見ることができたり、かかりつけ医にメッセージを送ることができるシステムは、患者さんが自分自身の疾患について把握することができ、また診察時には質問できなかったことも思いついた時に訊くことができる良いシステムであると思いました。
・患者さんも主訴を医師に伝える際は母国語の方が細かいニュアンスをうまく伝えられると仰っていましたが、患者さんの訴えを引き出したり、患者さんに伝わるように話すには言葉の表現力を磨くことも大切なことだと感じました。
・今回の研修では初めて訪れた街で一人で行動することも多く、不安なこともありましたが、丁寧にご指導してくださった先生方、快く迎え入れてくださったスタッフの皆様に出会えて、挑戦してよかったなと感じております。
・今回の研修で得たことを来年度離島診療所へ赴任した際に活かせるよう、まずは目の前の患者さんに丁寧に向き合っていきたいと考えております。
・研修準備の段階から研修修了まで関わってくださったすべての方々に感謝申し上げます。
・この度はとても貴重な機会を設けてくださり、本当にありがとうございました。
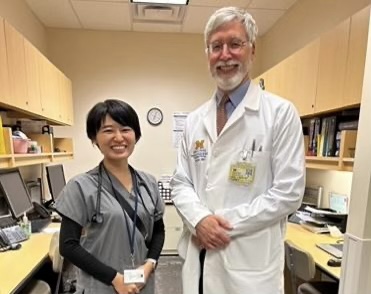 Dr.Rew
Dr.Rew
 Dr.Kiyota
Dr.Kiyota
 Dr.Beduhn
Dr.Beduhn
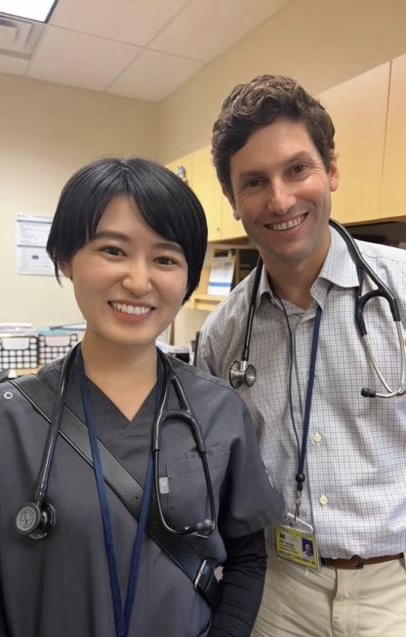 Dr.Shumer
Dr.Shumer
 Dr.Wakai
Dr.Wakai
 Dr.Hashikawa
Dr.Hashikawa
 お世話になった方々
お世話になった方々
 Dr.Little
Dr.Little
